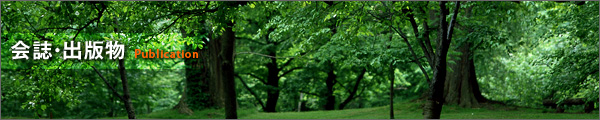人は万物の霊長?
虫めがね vol.39 No.2 (2013)
人は「万物の霊長である」と自称している。はたしてそうであろうか。
人は言葉をしゃべることが出来ることをその理由の一つとしているが、アフリカのジャングルに住むチンパンジーは三十五語くらいの言葉を使いわけて、仲間とコミュニケーションをとっているらしいことが判っている。わが家には十五年くらい前から犬を飼っているが、散歩に行きたい時、トイレに行きたい時、寒い時、不審な者が現われた時など、微妙に鳴き声を変えて知らせてくれる。夏に木に止まって鳴くセミは、何種類か鳴き方を変えて求愛とか警告とかのコミュニケーションをとっている。人が言葉をしゃべるということは、他の生物と比較して使える語彙数が多いという量的な違いであって質的な違いではなさそうだ。
人は家畜を飼育したり、農業を行い、食糧を将来の為に貯えるというのが他の生物より優れていると考えられている。これもアリはアブラムシ(アリマキ)を保護し飼育して、アブラムシが出す甘露(糖液)を得ている。ある種のキツツキ、カラス、ネズミは豊富な時期に収穫した食糧を貯え、乏しくなった時に、その貯えを引き出して食べることが知られている。
人は道具を使って自分の生活を便利にしている。ガラパゴス諸島にすむキツツキフィンチはサボテンのとげを口ばしにくわえて、その先を木の穴に突っ込んで、中にいる虫を追い出して、その虫を食べている。カラスが木の実を道路に並べて、その上を自動車が通り、タイヤに敷かれて割れた実の中味を食べているのをテレビで見たことがある。チンパンジーは石を使って硬い実を割って食べることがある。これらは動物も道具を使っている例といえよう。
子を産んで育てるという行為はすべての動物が共通に行っていることで、人の特技ではあるまい。自分の子ども達を一人立ちできるように教育することも、トラやライオンなど、いろいろな動物が自分の子どもたちに獲物の捕らえ方を教えている行為と同じである。
こう考えてみると、人が「万物の霊長」である、その根拠は薄弱になってくる。
ところが、最近ある動物園の園長から次のような話を聞いた。
「親が子どもの面倒をみて、育てるのは多くの動物で見ることが出来る。しかし、その子どもが成長して、年老いた親の世話をするのは人間だけです」
これは「万物の霊長」と胸をはって言える根拠かもしれない。
「年老いた 親のしあわせ わがしあわせ」
(赤タイ)
飲料自動販売機内に昆虫がいる!
虫めがね vol.39 No.1 (2013)
筆者が勤務している大学の卒業研究の一つとして飲料自動販売機内に侵入する昆虫について調査することにした。過去の文献を調べてみると、自販機の下や周辺の昆虫類を調査した報告はいくつかあるが、実際に自販機内部の昆虫を調査した報告はなかった。それで、学内に設置してある自販機会社の数社に電話して、「学生の教育の一環としての卒業研究だから協力してくれ」と、難色を示す業者を説得して、自販機内に昆虫捕獲器を置くことを了承してもらった。
気候が良い五月の時期に、学内に設置してある六台の自販機の内部に、粘着式の昆虫捕獲器を八日間置いた。その結果、夜間に飛来して集まってくるコバエ類が最も多く捕まった。歩行性昆虫であるクロゴキブリやアリ類も捕まった。下水溝や汚水槽など汚れた水域を繁殖場所としているチョウバエも捕まった。同時に行った自販機下の調査では、もっと多くの昆虫類が捕まったが、さすがに内部にまで侵入する昆虫は大幅に減っていた。それでも、調査した六台の自販機で昆虫が一匹も捕まらなかったものは無かった。
更に、これらの捕獲した昆虫類が体表にどんな食中毒原因菌をつけているかを調べてみた。その結果、クロゴキブリからは、動物の腸管内に分布しており、家畜の糞便などから汚染するサルモネラが検出された。コバエの体表からは、土壌などの自然環境に存在するセレウス菌が検出された。従って、自販機の内部に侵入した昆虫類が機内で歩き回って飲料と接触すれば、その飲料は汚染される可能性があるわけだ。
考えてみると、屋外に置いてある自販機は昆虫類にとっては侵入したくなる条件がそろっている。まず、夜間でも自販機には明かりがついている。走光性の昆虫たちにとっては誘虫灯みたいなもので、遠くからもこの光を目指して飛んでくる。また、内部は暖かい。夜間に外気温が下がってくると、暖かい場所を求めてゴキブリなどの歩行性昆虫が侵入してくる。更には、カップ式の飲料自販機の場合、内部に侵入した昆虫たちはその美味しい飲み物をなめることが出来る。三拍子がそろっているわけだ。
ただ、最近の自販機を見ると、缶入りや紙パック入りの飲料がほとんどであり、カップ式は少なくなっているので、あまり心配はしていない。
(赤タイ)
味覚センサー
虫めがね vol.38 No.6 (2012)
人は甘い、酸っぱい、旨い、苦いなど、食品の味を見分ける能力を持っている。これは甘いもの(糖分)はエネルギー源であり、旨いもの(アミノ酸など)は体の構成に必要なものだから沢山とろう。苦いもの(アルカロイドなど)や酸っぱいもの(腐ったもの)は体に悪いので食べないようにしようという、自己維持の為のセンサーと考えられる。
子どもたちは大人に比べて、甘みのセンサーの感度が高く、甘いものが大好きである。これは、子どもは活動が活発であり、それだけエネルギーが多く必要なことを示している。
人類が地球上に誕生して、約五百万年経つ。森林の木の実や根、草原の昆虫や小動物などを食べながら生きてきた。その間に、ある人は食べてはいけないものを食べて、食中毒などで死んでいった。その子孫は当然残らなかった。味覚センサーが鋭く、有害なものを的確に見分けた人は生き延びて、現在の我々の先祖となった。
このような味覚センサーは、人間に特有のものではない。我が家で十年以上飼っているメス犬がいるが、かの女は食べて良いものかどうかを鋭い嗅覚で識別している。腐ったものは食べない。それだけではなく、体調が悪いときなどは、草むらに入り、日ごろ食べもしない雑草をむしゃむしゃ食べている。解毒剤だろうか。誰かが教えるわけでもないが、漢方薬的に雑草を食べているようだ。
エストリアとロシアの国境沿いにペイプシ湖という大きな湖がある。二十世紀の中ごろ、この湖のある無人島で野生のサルやチンパンジー、オランウータンを放って自然に飼育した。これらの動物は各地から集められたものなので、この無人島は未知の場所である。この未知の場所で木の実や草の根を食べ、昆虫や小動物を食べて生活したわけである。植物や小動物・昆虫の種類は豊富であるが、その中には有毒な植物や有害な昆虫類も沢山あった。ところが、ここに放たれたサルたちは、これらの有毒・有害なものを食べて体調を悪くしたり、死んだりしたものは一頭もいなかったそうだ。人類は約五百万年前に、彼らと共通の祖先から分かれて人類として進化していったが、現代人はこれらのサルたちのような鋭い味覚センサーはもはや持ち合わせていないだろう。現代の我々は食べられる植物として栽培された野菜や果物、漁師が獲ってきてくれた魚や、肉屋が提供してくれる肉類など、食べ物の有害・有毒は、今や他人に依存しており、自分で判別することはほとんど無くなった。それゆえ個人の味覚センサーの鋭鈍が生死に直結することは無くなった。それだけではなく、祖先たちが避けてきた辛い味の食品を、キムチや激辛ラーメンとか言って食べているし、苦い抹茶や、コーヒーを楽しんでいるという変な生物に進化した。
(赤タイ)
馬と鹿
虫めがね vol.38 No.5 (2012)
宮崎県の南の端、鹿児島県と接するところに串間市がある。そこに全国でも珍しい野生馬の生息地「都井岬」がある。ここに、約八十頭の野生馬が生息している。これは、江戸時代に高鍋藩秋月家が軍馬を生産するために、この岬に放牧したことに始まる。当初から自由放牧、自然繁殖させていたが、それがそのまま野生化したものである。野生馬なので自然に生まれ自然に育ち自然に一生を終える。餌を与えたり、馬小屋を造るなどの人の手は加えられていない。串間市の職員で、この岬馬を管理しておられる秋田優氏の案内でこの岬馬を見学した。
ここは馬としては唯一、「自然における特有の動物群集」として、国の天然記念物に指定されている。オス一頭に対してメス二~三頭でハーレムを形成し、これに子馬が入って五~六頭で群れを作って行動している。餌となる牧草や飲み水を求めて、つぎにどこに移動するかなどは、子馬を伴っている雌馬が決める。その場合、年長の雌馬が主導権を握る。リーダーの雄馬は自分のハーレムを後方から見守り、外敵や他の馬の群れとの諍いが起こらないように見張っている、また、繁殖期間中は、オスは自分のハーレムのメスの排泄物に自分の尿をかけて、他の雄馬が興味を示さないように、繁殖に関する匂い情報を消してしまうなど、興味深い説明を受けた。
ところが、この野生馬の群れの中に、いつの頃からか一頭の牡鹿が紛れ込んで共存して生活している。お互いケンカもせず、居心地が良いのか鹿はここから立ち去ろうともしないし、馬の方も何の警戒心も示さない。お互い利害関係がない為であろう。馬と鹿にとってはそうかもしれないが、日本語を話す人にとっては馬と鹿の共存はある意味を持ってくる。「馬鹿者」、「馬鹿なことをする」などである。ここでの共存を見ていると、馬鹿な仲間とは思えない。両者は自然に溶け込んでのどかに生活している。
馬鹿の語源には諸説あるようだ。史記の「鹿を指して馬という」の故事を語源とする説が最もわかりやすく普及しているが、サンスクリット語(梵語)で「愚か、痴」を意味するmohaの音写である「莫迦(ばくか)」であり、馬鹿はその当て字であるというのが正しいようだ。つまり仏教とともに、わが国に入ってきた言葉で、馬鹿は単にその音を当てはめたわけで、馬と鹿にとっては、大変迷惑な話である。
ただ、映画の「釣りバカ日誌」や、「親ばか」、「バカ当たり」など、必ずしも悪くない意味で使われる例もある。都井岬の例は「ばかに仲の良い馬と鹿」と言えるかもしれない。
(赤タイ)
ノミとはどんな虫ですか?
虫めがね vol.38 No.4 (2012)
ノミ・シラミ 馬の尿する枕元
と江戸時代の俳聖松尾芭蕉が詠んでいる。このようにノミやシラミは人々の身ぢかで、生活の中にいる昆虫であった。私は終戦まもない頃に少年時代をすごしたが、夜、寝ていると、何となく脚のあたりがかゆくなったので、ふとんをパッとめくるとノミがピョンと飛び出てきた。急いでそれを捕まえて爪の上に置いてパチンとつぶすと、吸血していた血がジュとノミから出てくる。コヤツ俺の大切な血液を吸ったにっくき奴と、仇でも獲った気持ちになったものだ。
先日、東京のある大学で衛生害虫についての話をした。そして、
「何か質問はありませんか」
と尋ねると、ある学生が手を上げて、
「ノミはどのくらいの大きさの害虫ですか。また、どのような害があるのですか」
であった。
この質問は私にとって想定外であった。ノミは身近な害虫で誰でも知っていると何となく思って話していたわけである。しかし、良く考えてみると無理もない。現代の日本の若者たちはノミにお目にかかったことがない人が多いであろう。昔(私の少年時代頃まで)はノミは世間の常識であり、ほぼ、どこの家庭にでもいた。その頃、薬局に行けばどこでも買えたノミ取粉(殺虫粉剤)も、今ではもう売れないので薬局では買えまい。
ノミに吸血されると刺されたところが赤く腫れてかゆくなります。これがひどくなるとアレルギー性皮膚炎になることもあります。私たち人間は、そこで殺虫剤などでノミ退治をします。しかし、ペットや家畜などは、自分では駆除できないので、常時吸血され続けるとストレスになり食欲がなくなり、元気がなくなることがあります。ある畜産農家の乳牛が元気がなくなり、ミルクの出が悪くなったので詳しく原因を調べると、その乳牛の体に数百匹近いノミが寄生していたという報告がある。また、ある種のノミはペストや発疹熱のベクター(病原体媒介昆虫)であり、ノミの大繁殖は人へのペストの大流行の原因となります、などを説明したら納得した。
「害虫は時代によって、場所によって異なるのだ」と説明している私自身が、時代によって異なるのだと納得した場面であった。
(赤タイ)